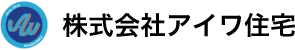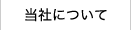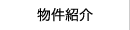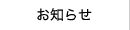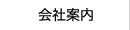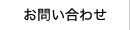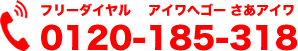不動産取得税
■ 不動産取得税とは?
不動産(土地や建物)を有償または無償で取得したときに課される税金です。都道府県が課税主体で、一度きりの税金です。
■ どんなときにかかるの?
不動産を購入した ✅ かかる
新築・建売住宅を購入 ✅ かかる
建物を新築した ✅ かかる
相続で取得した ❌ かからない
贈与で取得した ✅ かかる(ただし別途、贈与税も)
■ 税額の計算方法
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
■ 標準税率:
- 土地・建物ともに 4%
※ただし、軽減措置により以下のように軽減されるケースが多いです。
■ 主な軽減措置(住宅用の場合)
◎ 新築住宅の場合:
- 税率:3% に軽減
- 建物の評価額から1,200万円の控除(一定条件あり)
◎ 土地の軽減:
- 課税標準額から控除あり(計算が少し複雑)
- 例:一定の面積以下の宅地であれば1/2に減額
◎ 中古住宅の軽減(条件あり):
- 耐震基準を満たす住宅(昭和57年以降の建築など)であれば控除対象に
- 建築年数や用途によって異なるので、都道府県税事務所に確認が安心
■ 支払いのタイミングと方法
- 不動産を取得してから数か月後に納税通知書が届く
- 通常は都道府県税事務所から送られてきます
- コンビニや銀行、スマホ決済などで支払い可能
■ 注意点
- 固定資産税評価額は、市場価格とは異なるため注意
- 軽減措置を受けるには申告が必要な場合もあるので、通知書を受け取ったら内容をよく確認
- 贈与による取得は、贈与税も別途かかる場合あり
■ 相談先
- お住まいの都道府県税事務所
自宅を売った時の3,000万円特別控除
「居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用不動産)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる制度です。以下に詳しく解説します
■ 3,000万円特別控除とは?
マイホーム(居住用の住宅や土地)を売却した際の譲渡益から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
■ 適用されるケース
- 本人やその家族が実際に住んでいた住宅を売却した場合
- 住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
■適用要件(主な条件)
- 売却した不動産が本人の居住用財産であること
- 実際に住んでいたマイホームが対象です(別荘などは対象外)
- 過去に同じ特例を使っていないこと
- 同じ特例を使ってから2年を経過していない場合は再利用不可
- 家屋を取り壊した後でもOK
- 売却前に建物を取り壊しても、取り壊し後から1年以内に売却すれば適用可
- 親子や夫婦間など特別な関係にある人への売却ではないこと
■ 控除の計算方法(簡単な例)
例)
マイホームの売却価格:5,000万円
取得費(購入価格):2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):200万円
【譲渡所得】
= 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 5,000万 -(2,000万 + 200万)= 2,800万円
【特別控除適用後】
2,800万円 - 3,000万円 → 所得ゼロ(課税されません)
■ 他の特例との併用について
- 「軽減税率の特例」とは併用できません
- 「買換え特例」などとは併用不可
- どの特例を使うか、慎重な選択が必要です(税理士に相談をおすすめ)
■ 手続きの方法
- 確定申告が必要です!
- 売却した翌年の2月16日~3月15日に申告
- 「譲渡所得の内訳書」などを添付
■ 注意点
- 空き家になってから長期間放置していた場合は適用できないことがあります
- 一時的な引越しで住んでいなかった期間も考慮されます
不明点があれば、税務署や税理士に相談するのが安心ですよ?
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
固定資産税基準日
日本の会計年度(または学校年度など)は一般的に4月から翌年3月までですが、固定資産税の課税基準日は「1月1日」と定められています。
1月1日が基準日
日本の地方税法によって定められています。
- 固定資産税は、その年の1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産など)を所有している人に課税されます。
- 1月1日を基準日にし、全国一律のルールで課税されます。
- 実際の納税通知書は多くの自治体で4月~6月ごろに送付され、納付は年4回の分納が多いです(6月、9月、12月、翌年2月など)。
ポイントまとめ
会計年度 4月1日~翌年3月31日
固定資産税の課税基準日 1月1日
納税通知書の送付時期 通常4~6月頃
納付方法 一括または年4回の分納
「年度」と「課税基準日」は、ずれが生じます。
空家の3,000万円特別控除 耐震リフォーム
■相続人3人以上は2,000万円控除に
2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。
これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。
◆ ポイントまとめ
◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円
譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)
◆変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円
相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円
譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに
◆該当するかを確認する方法
- 譲渡日が2024年1月1日以降であること
- 相続人が3人以上いるかどうか
- 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
- 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること
これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。
■国税庁公式解説より(改正内容抜粋)
被相続人居住用家屋等の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例については、
譲渡時までに耐震改修工事が完了していない場合でも、譲渡日から翌年2月15日までに買主が耐震改修を完了し、証明書を取得したときは適用可能 となる。(令和6年度税制改正)
✔️ 令和6年4月1日以降の譲渡分で
✔️ 買主が翌年2月15日までに耐震改修+証明書取得する
■特例の適用を受けるための要件ハの(イ)(ロ)(ハ)の(ロ)
(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。
■空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと、
売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています
■ ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須
これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。
① 建物を残して売る場合
- 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。
② 建物を壊して土地として売る場合:
- 売却前に建物を解体して更地にする。
■ 国税庁の公式記載(要約)
昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること
■ 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間
- 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
- そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます
つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。
登録免許税
「登録免許税(とうろくめんきょぜい)」とは、登記や登録を行う際に課される国税の一つで、主に不動産の登記や会社の設立・変更などの登記をする際に必要になります
■ 登録免許税の概要
項 目 内 容
税の種類 国税(申告納税方式ではなく、登記時に自動的に課される)
管 轄 法務局などの登記機関での手続き時に納付
納付方法 登記申請時に収入印紙などで納付
課税対象 不動産登記、法人登記、船舶・航空機の登録不など
■ 具体的な例(主なもの)
登録内容 税 率(原則) 備考
不動産の所有権移転登記 固定資産評価額の2.0% 相続:0.4% 贈与:2.0%
会社設立(株式会社) 資本金の0.7%(最低15万円) 合同会社は6万円(定額)
不動産の抵当権設定登記 債権金額の0.4% 住宅ローンなど
※上記税率は法改正により変更される場合があります
■ 減税・免税措置
住宅取得時や特定の条件を満たす場合、軽減税率や非課税措置が適用されることもあります。
【例】
- 新築住宅の所有権保存登記 → 0.15%(軽減措置あり)
- 特定の法人設立支援制度を利用した場合の登録免許税の減免 など
ご自身のケースに当てはめた試算もできますので、気になる場合は具体的な内容を教えてください。
参考:国税庁 登録免許税の概要
譲渡所得に関わる購入時建物減価償却
2025/3/20作成
譲渡所得(たとえば不動産を売却したときの利益)を計算する際、建物の取得費は「減価償却後の価額」を用いる必要があります。つまり、売却するまでに行った減価償却費は、取得費から差し引くということです。
■ 譲渡所得の計算式(基本)
譲渡所得=譲渡価額(売却額)−(取得費+譲渡費用)譲渡所得
◆「取得費」には要注意!
建物の場合、取得費=建物の取得価格 − 減価償却費の合計 です。
■ 建物の減価償却費(譲渡所得用)の計算方法
✅ 基本の計算式
減価償却費=取得価額×償却率×経過年数(1年未満切上げ)
※ここでいう「償却率」は、所得税法上の定額法の償却率を使用します(税法で定められた耐用年数に基づく)
■ 計算例
<例>木造住宅(住宅用)
取得価額 1,000万円、所有期間 8年、償却率 0.031(=耐用年数22年)
減価償却費=1,000万円×0.031×8年=248万円減価償却費
取得費=1,000万円−248万円=752万円(←これを譲渡所得の計算に使う)
■よくある注意点
| ポイント | 説明 |
|---|---|
| 減価償却は「していなくても計算される」 | 実際に経費計上していなくても、自動的に減価償却されたものとみなされます(みなし償却) |
| 土地部分は減価償却しない | 取得費を土地と建物に按分する必要があります |
| 相続・贈与で取得した場合 | 前所有者の取得価額・取得時期を引き継ぐケースが多いです |
■ 土地と建物の按分方法(参考)
不動産の売買契約書に土地・建物の内訳が書かれていれば、それに従って按分します。なければ、固定資産税評価額などを元に按分します。
より正確な試算が必要であれば、以下の情報があると計算がしやすいです:
- 建物の取得年月・価格
- 建物の構造(木造・RCなど)
- 売却時期
- 土地と建物の割合(または固定資産税評価額)