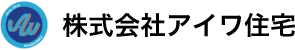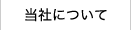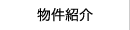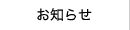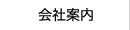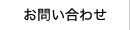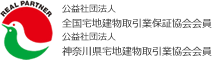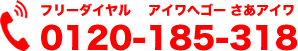年末調整、確定申告
年末調整とは?
「年末調整」は、会社員や公務員など給与所得者のために、会社が税金の過不足を調整する手続きです。
□特徴
- 対象:主に給与所得者(会社員など)
- 実施時期:12月(給与支払者が行う)
- 手続き:社員が「扶養控除申告書」などを提出し、会社が税金を計算
- 結果:源泉徴収で多く納めていれば還付、少なければ徴収
□控除対象例
- 配偶者控除、扶養控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除 など
確定申告とは?
「確定申告」は、1年間の所得を自分で計算して、税務署に申告する制度です。
□特徴
- 対象:以下のような人
- 自営業、フリーランス
- 年収2,000万円超の給与所得者
- 給与以外に副収入がある人(副業など)
- 医療費控除、寄付金控除、住宅ローン控除初年度 など
- 実施時期:毎年2月16日〜3月15日
- 方法:e-Tax(電子申告)や紙での提出が可能
□控除や申告の目的
- 税金の還付(払いすぎた税金が戻る)
- 追加納税(足りなかった分を納める)
年末調整と確定申告の関係
- 会社員で年末調整だけで完結する人は、確定申告の必要なし
- 年末調整を受けた人でも、医療費控除やふるさと納税をした場合は、確定申告で還付が受けられることも
物件のご案内について
◆株式会社アイワ住宅のご案内方法について
当社では、お客様のご希望に合わせて3つのご案内コースをご用意しております。
◆ ご案内コース(お選びください)
- Aコース:この物件だけを1時間以内でサクッと内覧したい方
- Bコース:時間を気にせず、じっくりと内覧&ご相談したい方
- Cコース:この物件に加え、他の物件も一緒に見てみたい方
※ご案内の際は、お客様のペースを大切にし、無理な営業は一切いたしません。
■不動産に関する暮らしと安心にお答えします
不動産にまつわるさまざまな疑問や不安に、専門家の視点からわかりやすく解説します。
1. 住宅ローンと家計管理
「ローンを組むと節約できる?」―賢い家計見直し術とは?
住宅ローンは負担?それとも家計改善のチャンス?資金計画の見直し方をお伝えします。
2. 家賃保証制度の基礎知識
「連帯保証人なしでも借りられる時代へ」―保証会社の役割とは?
現代の賃貸事情に欠かせない保証会社。その仕組みとメリットを解説します。
3. 外国人の方の賃貸契約
「外国籍でも安心」―日本の物件を借りるためのポイント
外国人の方がスムーズに物件を借りるために必要な書類や手続きのコツをご紹介。
4.(※番号抜けのため追記をおすすめ)シニア世代の住み替えや住まいの工夫
「人生100年時代」―安心して暮らせる住まいづくりとは?
将来を見据えた住み替えやリフォームのポイントを解説します。
5. お子様のいないご夫婦の相続対策
「配偶者だけが相続するとは限らない!」―知っておきたい遺言と法定相続
大切な資産を守るために、早めに知っておきたい相続の基礎知識。
6. 不動産購入時のプロのサポート
「不動産選びはプロと一緒に」―FP資格者が教える住まいとライフプラン
人生設計に合った住まい選びには、専門家のサポートが欠かせません。
7. 建築・リフォームのご相談窓口
「住まいは買って終わりじゃない」―快適に暮らすための工事とメンテナンス
暮らしをより良くするための工事・リフォーム相談を承ります。
不動産取得税
■ 不動産取得税とは?
不動産(土地や建物)を有償または無償で取得したときに課される税金です。都道府県が課税主体で、一度きりの税金です。
■ どんなときにかかるの?
不動産を購入した ✅ かかる
新築・建売住宅を購入 ✅ かかる
建物を新築した ✅ かかる
相続で取得した ❌ かからない
贈与で取得した ✅ かかる(ただし別途、贈与税も)
■ 税額の計算方法
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
■ 標準税率:
- 土地・建物ともに 4%
※ただし、軽減措置により以下のように軽減されるケースが多いです。
■ 主な軽減措置(住宅用の場合)
◎ 新築住宅の場合:
- 税率:3% に軽減
- 建物の評価額から1,200万円の控除(一定条件あり)
◎ 土地の軽減:
- 課税標準額から控除あり(計算が少し複雑)
- 例:一定の面積以下の宅地であれば1/2に減額
◎ 中古住宅の軽減(条件あり):
- 耐震基準を満たす住宅(昭和57年以降の建築など)であれば控除対象に
- 建築年数や用途によって異なるので、都道府県税事務所に確認が安心
■ 支払いのタイミングと方法
- 不動産を取得してから数か月後に納税通知書が届く
- 通常は都道府県税事務所から送られてきます
- コンビニや銀行、スマホ決済などで支払い可能
■ 注意点
- 固定資産税評価額は、市場価格とは異なるため注意
- 軽減措置を受けるには申告が必要な場合もあるので、通知書を受け取ったら内容をよく確認
- 贈与による取得は、贈与税も別途かかる場合あり
■ 相談先
- お住まいの都道府県税事務所
不動産無料相談所
神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています
■相模南支部 不動産無料相談所
- 開催日時:毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
- 相談時間:1人30分(15:30に面談終了)
- 場所:〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
- アクセス:小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
- 予約方法:完全予約制。電話、FAX、またはEメールで予約が必要です。
- 電話:042-743-3276
- FAX:042-749-1965
- Eメール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
- ※相談日前日の17時が予約締切です
- ■相模原市役所での不動産無料相談
相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。
中央区役所
- 開催日:第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:中央区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-769-8230
南区役所
- 開催日:第1月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:南区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-749-2171
緑区役所
- 開催日:第3月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:緑区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-775-1773
不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください
市及び協会相談員
相模原市の空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として活動しています。
空き家の管理・活用・売却、相続後の不動産の整理など、「誰に相談していいかわからない」問題を、現場目線でサポートします。
売却ありきではなく、状況に応じた最適な選択肢をご提案します。
まずはお気軽にご相談ください。
神奈川県宅地建物取引業協会 相模南支部では、不動産に関する無料相談を実施しています
■相模南支部 不動産無料相談所
- 開催日時:毎月第2火曜日(5月・8月および祝日を除く)13:30~15:30
- 相談時間:1人30分(15:30に面談終了)
- 場所:〒252-0303 神奈川県相模原市南区相模大野3-17-18 サンハイツ相模大野第2 401
- アクセス:小田急小田原線 相模大野駅北口より徒歩3分
- 予約方法:完全予約制。電話、FAX、またはEメールで予約が必要です。
- 電話:042-743-3276
- FAX:042-749-1965
- Eメール:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
- 受付時間:月~金 9:00~12:00、13:00~17:00(土日祝日・夏季・年末年始休暇を除く)
- ※相談日前日の17時が予約締切です
- ■相模原市役所での不動産無料相談
相模原市では、各区役所で不動産無料相談を実施しています。
中央区役所
- 開催日:第2金曜日・第4月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:中央区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-769-8230
南区役所
- 開催日:第1月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:南区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-749-2171
緑区役所
- 開催日:第3月曜日(祝日を除く)
- 時間:13:30~16:00(1人30分以内)
- 場所:緑区役所市民相談室
- 予約方法:当日の午前8時30分から電話で予約(先着順)
- 申込先:政策課 市民相談室 042-775-1773
不動産の売買、賃貸、相続、契約トラブルなど、さまざまな相談に対応しています。専門の相談員が対応しますので、お気軽にご利用ください
一般のお客様向け 有料個別相談のご案内
一般のお客様向け 有料個別相談のご案内
当事務所では、一般のお客様を対象に
空き家・相続不動産・売却や活用に関する有料個別相談を行っております。
相模原市空家等相談員、神奈川県宅地建物取引業相談員として、
行政相談・民間取引の両方に携わってきた経験をもとに、
一人ひとりの状況に合わせた現実的で具体的なアドバイスを行います。
「売るべきか残すべきか判断できない」
「相続したが、何から手を付ければよいかわからない」
「業者の話が正しいのか、第三者の意見がほしい」
このようなお悩みを、30分という限られた時間の中で
状況整理 → 選択肢の提示 → 今後の進め方まで分かりやすくご説明します。
有料相談の特徴
- 売却・媒介契約を前提としない、中立的な立場での相談
- 空き家の管理・活用・売却を含めた総合的な視点
- 図面・資料・登記内容を見ながらの具体的な助言
- 「今すぐやること」「急がなくてよいこと」を整理
無料相談では踏み込めない内容まで対応いたします。
料金・相談方法
相談料:30分 5,500円(税込)
完全予約制となります。
※30分単位での延長も可能です(事前にご相談ください)
※対面・オンラインいずれも対応可能です
ご利用にあたって
- 法律・税務に関する最終判断は、弁護士・税理士等の専門家への相談をおすすめする場合があります
- 無理な営業・契約の勧誘は行いません
- 相談内容の秘密は厳守いたします
こんな方におすすめです
- 空き家・相続不動産について、まず整理したい方
- 不動産会社の提案に不安があり、セカンドオピニオンがほしい方
- 具体的な方向性だけでも決めておきたい方
- ※上部の右端タブ「お問い合わせ」をクリックして下さい。
プロの方向け|売買実務相談
プロの方向け|売買実務相談
実体験に基づく不動産売買の専門アドバイス
宅地建物取引業者として、主に売主の立場で1,200棟以上の不動産取引に関与してきました。
不動産業界歴36年。机上論ではなく、現場で積み上げてきた「実体験」に基づく情報をご提供します。
現在、インターネット上には新旧さまざまな情報が混在しており、AIによる要約情報も増えています。
しかし、実際の取引現場では、現地・行政・買主対応など、経験でしか判断できない場面が数多く存在します。
本相談では、そうした現場で起きた実例をもとに、広告・売買実務に関する具体的なアドバイスを行います。
提供する知識・アドバイスの一例
- 高低差のある土地に関する実務対応
(防護壁、切土2m超・盛土1m超、敷地延長時の注意点 等) - 実績・経験の浅い方への実務アドバイス
- 賃貸業中心の方が売買契約を行う際の注意点
- 広告表現・重要事項説明での実務上の判断ポイント
※一般論ではなく、実際に対応した事例ベースでお話しします。
ご相談について
- 相談料:1時間11,000円(税込)
- 完全予約制
- ご相談依頼は メールのみ で承ります
Email:このメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
※通常業務を優先しておりますため、お電話でのご連絡はご遠慮ください。
内容確認後、こちらから折り返しご連絡いたします。
※上部の右端タブ「お問い合わせ」をクリックして下さい。
自宅を売った時の3,000万円特別控除
「居住用財産を売ったときの3,000万円特別控除」は、マイホーム(居住用不動産)を売却したときに得た利益(譲渡所得)から最大3,000万円を控除できる制度です。以下に詳しく解説します
■ 3,000万円特別控除とは?
マイホーム(居住用の住宅や土地)を売却した際の譲渡益から、最大3,000万円まで控除できる制度です。
■ 適用されるケース
- 本人やその家族が実際に住んでいた住宅を売却した場合
- 住まなくなってから3年目の年末までに売却した場合
■適用要件(主な条件)
- 売却した不動産が本人の居住用財産であること
- 実際に住んでいたマイホームが対象です(別荘などは対象外)
- 過去に同じ特例を使っていないこと
- 同じ特例を使ってから2年を経過していない場合は再利用不可
- 家屋を取り壊した後でもOK
- 売却前に建物を取り壊しても、取り壊し後から1年以内に売却すれば適用可
- 親子や夫婦間など特別な関係にある人への売却ではないこと
■ 控除の計算方法(簡単な例)
例)
マイホームの売却価格:5,000万円
取得費(購入価格):2,000万円
譲渡費用(仲介手数料など):200万円
【譲渡所得】
= 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)
= 5,000万 -(2,000万 + 200万)= 2,800万円
【特別控除適用後】
2,800万円 - 3,000万円 → 所得ゼロ(課税されません)
■ 他の特例との併用について
- 「軽減税率の特例」とは併用できません
- 「買換え特例」などとは併用不可
- どの特例を使うか、慎重な選択が必要です(税理士に相談をおすすめ)
■ 手続きの方法
- 確定申告が必要です!
- 売却した翌年の2月16日~3月15日に申告
- 「譲渡所得の内訳書」などを添付
■ 注意点
- 空き家になってから長期間放置していた場合は適用できないことがあります
- 一時的な引越しで住んでいなかった期間も考慮されます
不明点があれば、税務署や税理士に相談するのが安心ですよ?
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。国税局HPより
薬の一包化
薬の一包化(いっぽうか)・一括袋詰めについて
薬局で処方された複数の錠剤やカプセルを、1回分ずつまとめて1袋に分包することを「一包化」といいます。この方法により、薬の飲み間違いや飲み忘れを防ぐことができ、特に薬の種類が多い高齢者にとっては、服薬管理が大幅にしやすくなります。
また、薬を個別に袋詰めするのではなく、すべての薬をひとつの袋にまとめて受け取ることで、持ち運びや保管も簡単になり、薬の紛失防止にもつながります。一包化は薬剤師による対応が必要ですが、希望すれば多くの薬局で依頼することが可能です。
航空法
航空法(こうくうほう)は、日本の空の安全を確保し、航空機の運航や空港の管理、航空従事者の資格などを定めた法律です。正式名称は「航空法(昭和27年法律第231号)」で、所管は国土交通省
航空法の目的
- 航空の安全確保
- 航空機の円滑な運航
- 人命・財産の保護
主な内容(ポイント別)
□ 航空機の定義と分類
- 航空機:人が乗って飛行できる装置(飛行機・ヘリコプターなど)
- 無人航空機(ドローン等):近年の改正で厳格に規制対象化
□ 飛行ルール(空域・高度)
- 最低安全高度
- 市街地:原則 300m以上
- 人家の少ない地域:原則 150m以上
- 制限空域
- 空港周辺、人口集中地区(DID)、自衛隊・米軍施設周辺 など
- 夜間・目視外飛行は原則禁止(許可制)
□ 空港・飛行場の規制
- 空港周辺の高さ制限
- 建築物・クレーン・広告塔などは制限対象
- 障害物の設置制限
- 建築計画時に航空法の確認が必要なケースあり(不動産実務で重要)
□ 航空従事者の資格
- 操縦士(パイロット)
- 航空整備士
- 航空管制官
→ 国家資格・免許制
□ 無人航空機(ドローン)規制(重要)
- 100g以上は航空法の対象
- 原則禁止行為:
- 人口集中地区(DID)上空
- 夜間飛行
- 人・建物から30m未満
- 催し場所上空
- 国交省の許可・承認が必要な場合あり
-
□不動産・建築実務との関係(実務上の注意)
- 空港周辺土地
- 建物高さ制限 → 収益性・建築計画に影響
- クレーン・看板
- 一時的でも届出・制限対象になることあり
- ドローン撮影
- 物件撮影でも無許可飛行は違法の可能性
□関連法令(セットで確認)
- 建築基準法(高さ制限・用途地域)
- 小型無人機等飛行禁止法(重要施設周辺)
- 電波法(無線通信)
- □各自治体条例規制
-
- 空港名を指定した高さ制限
- 相模原・町田・大和エリアでの具体適用
- ドローン撮影を合法に行う方法
- 空港周辺土地