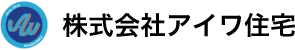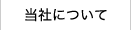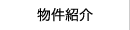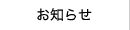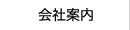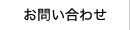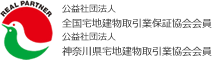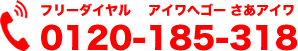告知義務
「超高齢化社会における不動産取引における孤独死の告知義務」について、国土交通省のガイドラインを基に説明します
■告知義務の基本的な考え方
2021年10月に国土交通省が公表した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」により、孤独死を含む人の死に関する告知義務の基準が明確化されました
■告知義務が原則不要なケース
- 自然死(老衰や病死)や、日常生活の中での不慮の事故死(転倒事故、誤嚥など)で、かつ特殊清掃等が行われていない場合は、原則として告知義務はありません。
自宅における死因のうち、老衰や病死による死亡が9割以上を占める一般的なものであるため、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性は低いと考えます
▲ 告知義務が必要となるケース
- 自殺、他殺、火災による死亡など、事件性のある死が発生した場合
- 自然死や不慮の事故死であっても、遺体の発見が遅れ、特殊清掃や大規模なリフォーム等が行われた場合。
- 死因が明らかでない場合(自然死か自殺・他殺か判断できない場合)
これらの場合、買主・借主の判断に重要な影響を及ぼす可能性があるため、告知義務が生じます
■告知義務の期間
- 賃貸借取引において、上記の告知義務が必要な事案が発生してから概ね3年が経過した後は、原則として告知義務は不要とされています。
- ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案については、3年経過後も告知が必要となる場合があります。
告知義務の有無や期間については、個別の事案の内容や社会的影響等を総合的に判断する必要があります。全宅連
■ 告知の方法と内容
- 告知を行う際には、事案の発生時期、場所、死因、特殊清掃等が行われた場合はその旨を伝える必要があります。
- ただし、亡くなった方やその遺族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はありません。
宅地建物取引業者は、売主・貸主に対して告知書等への適切な記載を求め、これを買主・借主に交付することが、トラブルの未然防止と迅速な解決のためにも有効です
■まとめ
▲自然死(老衰・病死)
告知義務原則不要 特殊清掃等が行われていない場合
▲日常生活の中での不慮の事故死
告知義務原則不要 特殊清掃等が行われていない場合
▲自殺・他殺・火災による死亡
告知義務必要 事件性があるため
▲自然死や不慮の事故死でも特殊清掃等が行われた場合
告知義務必要 遺体の発見が遅れた場合等
▲死因が明らかでない場合
告知義務必要 自然死か自殺・他殺か判断できない場合
▲告知義務が必要な事案発生から3年経過後(賃貸借取引)
告知義務原則不要 事件性、周知性、社会的影響等が特に高い場合を除く
■告知義務の有無や内容については、個別の事案の内容や社会的影響等を総合的に判断する必要があります
参考:「宅地建物取引業者による人の死の告知に関する ガイドライン」
令和3年10月 国土交通省 不動産・建設経済局 不動産業課
年数が経っている収益物件の購入時の注意点
年数が経っている収益物件の購入時の注意点
- 建物の構造と耐震性
- 1981年6月以降の「新耐震基準」適合物件かどうかを確認しましょう。
- 古い物件は耐震補強が必要なことが多く、その費用を見込んでおく必要があります。
- 修繕履歴とメンテナンス状況
- 定期的な修繕がされていない場合、外壁や屋根、配管設備に大きな修繕費がかかる可能性があります。
- 修繕記録(修繕履歴)を確認することが重要です。
- 設備の老朽化
- 給排水管・電気設備・エレベーターなどの交換時期に注意。
- 特に配管が古いと漏水リスクが高まります。
- 入居者の属性と入居率
- 長期入居者が多い場合、家賃が相場より低く抑えられているケースも。
- 空室率や滞納リスクもチェックしましょう。
- 法的制限・再建築可否
- 古い建物は接道義務を満たしておらず「再建築不可」の場合があります。
- これにより資産価値の下落や売却困難のリスクが生じます。
- 収支シミュレーションの見直し
- 購入後の修繕費や稼働率低下を見込んだ現実的なシミュレーションを行うことが大切です。
- 金融機関の評価
- 築年数が古いと金融機関の融資評価が厳しくなる場合があります。
- 物件評価額や融資年数の制限に影響します。
相模原市「盛土法」
【相模原市の盛土法について】
相模原市では、盛土法の施行により、市内全域の土地が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかに指定されており、すべての土地が盛土法の規制対象となっています。
そのため、宅地はもちろん、山林・農地・雑種地など土地の用途に関わらず、一定規模以上の盛土・切土・土砂の仮置きを行う場合には、事前に市への許可または届出が必要となる場合があります。
相模原市内には、過去に造成された宅地や高低差のある敷地、擁壁を伴う土地が多く存在しており、現況では問題がないように見える場合でも、盛土法の技術基準を満たしていないケースがあります。このような土地では、建替えや再造成、盛土の追加を行う際に、是正工事や計画変更が求められることがあります。
また、工事内容によっては、盛土法に基づく手続きが建築確認申請とは別に必要となり、事前協議や行政手続きに一定の期間を要する場合があります。そのため、建築計画や不動産取引においては、スケジュールに十分な余裕をもって検討することが重要です。
特に、緑区を中心とした丘陵地や傾斜地を含むエリアでは、排水計画や擁壁構造、安定計算の提出を求められる場合があり、工事費や工期に影響が出る可能性があります。
相模原市内で盛土や切土を伴う工事、または該当する可能性のある土地の売買をご検討の際は、早い段階で行政窓口や専門家へ相談し、法令遵守と安全性を十分に確認したうえで計画を進めてください。
収支シミュレーションの見直し
収支シミュレーションの見直し
築年数が経っている物件では、単純な「表面利回り」だけではリスクを見逃してしまうことがあります。
以下の点に注意して、より現実的なキャッシュフロー予測を立てる必要があります。
1. 修繕費の見込み
- 築古物件では、給排水管の交換や外壁塗装、屋根補修など大きな修繕が近づいていることが多いです。
- 数百万円単位の費用がかかる場合もあるため、事前に専門家に見積もりを依頼しておくと安心です。
2. 家賃下落の可能性
- 築年数が古くなるほど、家賃の下落リスクが高まります。
- 物件周辺の家賃相場と比較して、今後どの程度下がる可能性があるかを把握しましょう。
3. 空室率の上昇
- 築古物件は入居希望者が少なくなりがちで、空室期間が長期化することもあります。
- 地域の空室率や入居ニーズ(学生、単身者、高齢者など)も要チェックです。
4. 固定費の増加
- 古い物件は保険料が高くなる傾向があります。
- 管理費・修繕積立金(マンションの場合)も築年数とともに上がる場合があります。
5. 節税効果の過信に注意
- 築古物件は減価償却による節税メリットが強調されがちですが、実際の現金支出が多ければ赤字になる可能性も。
- 節税だけで判断せず、現金の出入り=実質収支に注目しましょう。
■現実的な収支シミュレーション例
年間家賃収入 600万円と仮定
空室ロス(10%) -60
管理費・共益費 -50
修繕積立・予備費 -80
固定資産税 -30
火災保険 -10
融資返済 -250
年間収支合計 +120
※ これは一例であり、実際はもっと詳細な項目と精度の高い見積もりが必要です。
築古物件を買うなら、「利回りが高い=儲かる」ではないことをしっかり意識し、「将来的な支出やリスクを織り込んだシミュレーション」が成功の鍵です。
固定資産税基準日
日本の会計年度(または学校年度など)は一般的に4月から翌年3月までですが、固定資産税の課税基準日は「1月1日」と定められています。
1月1日が基準日
日本の地方税法によって定められています。
- 固定資産税は、その年の1月1日現在で固定資産(土地・家屋・償却資産など)を所有している人に課税されます。
- 1月1日を基準日にし、全国一律のルールで課税されます。
- 実際の納税通知書は多くの自治体で4月~6月ごろに送付され、納付は年4回の分納が多いです(6月、9月、12月、翌年2月など)。
ポイントまとめ
会計年度 4月1日~翌年3月31日
固定資産税の課税基準日 1月1日
納税通知書の送付時期 通常4~6月頃
納付方法 一括または年4回の分納
「年度」と「課税基準日」は、ずれが生じます。
分 筆
分筆(ぶんぴつ)とは、不動産登記において一つの土地(筆)を複数の土地に分ける手続きのことを言います。
■ 分筆の基本情報
【1】なぜ分筆するの?
- 相続で土地を分けたいとき
- 売買や贈与で一部だけ譲渡したいとき
- 複数の用途に土地を分けて使いたいとき(例:住宅用・店舗用)
【2】分筆の条件
- 地目ごとに分ける(農地は農地として)
- 境界が確定している必要あり(隣地とのトラブル防止)
- 測量が必要(通常は土地家屋調査士が対応)
【3】必要な手続き
- 土地家屋調査士に依頼して測量・境界確認
- 分筆登記申請(法務局にて)
- 登記完了後、新たな地番が付き、それぞれ独立した不動産になります
【4】必要書類(一例)
- 登記申請書
- 分筆図(測量結果)
- 所有者の本人確認書類
- 委任状(代理人が申請する場合)
【5】注意点
- 市街化調整区域などでは制限がある場合も
- 農地の場合、「農地法の許可」が必要になることも
連帯保証人
賃貸契約に関する保証制度、特に連帯保証人制度の見直しについて、説明します。
1. 連帯保証人とは?
連帯保証人は、借主が賃料を支払わなかったり契約違反をした場合、借主と同じ責任を負う人です。債権者(この場合オーナーや管理会社)は、借主に請求せず直接連帯保証人に請求できるほど、責任が重い立場にあります。
2. 制度の見直し(民法改正)について
2020年4月1日に施行された改正民法により、個人が連帯保証人になる場合、次のような制限が加わりました。
■ 極度額の設定が義務化
- 個人が連帯保証人になる場合、「極度額」(保証の限度額)を契約書に明記しなければ、その保証契約は無効になります。
- これにより、連帯保証人は無制限な責任を負わされるリスクが軽減されました。
3. 極度額とは?
- 例えば、「極度額300万円」と明記されていれば、借主がいくら滞納しても、連帯保証人に請求できるのは最大300万円までです。
- 家賃が月10万円であれば、30か月分(=2年半)までの滞納分が限度、というイメージです。
4. 滞納が何か月で連帯保証人に通知されるか?
これは契約内容や管理会社の運用によります。一般的には:
- 1~2か月滞納時点で借主・連帯保証人に連絡が行くケースが多いです。
- 連帯保証人への通知義務は法律で明記されているわけではありませんが、適切なタイミングで通知することが求められています。
5. 2か月以上の支払義務違反と契約解除
- 契約書に「2か月以上賃料を滞納した場合、契約解除できる」とあれば、貸主はその時点で契約解除できます。
- しかし、貸主が何か月も滞納状態を放置した場合でも、連帯保証人に極度額までの請求はできます。
6. 空き家状態が続いていた場合は?
- 借主が退去せず、長期間家賃を滞納し続け、かつオーナーが対応しなかった場合でも、連帯保証人には極度額までの責任が生じる可能性があります。
- ただし、貸主の「損害拡大回避義務」に反する場合は、保証人の責任が軽減される可能性もあります。
まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 連帯保証人の責任 | 借主と同等。ただし極度額の範囲内。 |
| 極度額 | 契約時に必ず明記。上限のこと。 |
| 通知時期 | 多くは1~2か月の滞納で通知。 |
| 空き家が続いた場合 | 責任はあるが、貸主の対応状況によって減免可能性あり。 |
小規模宅地等の特例
「小規模宅地等の特例(しょうきぼたくちとうのとくれい)」について、相続税の節税においてとても重要な制度ですので、分かりやすくご説明します。
■小規模宅地等の特例とは?
相続した土地が「自宅」や「事業に使っていた土地」である場合、一定の条件を満たせば、相続税の課税評価額を最大80%減額できる特例制度です。
これは、残された家族が住み続けたり、事業を継続したりするのに過大な税負担がかからないようにするための措置です。
■どれくらい減額されるの?
自宅用地(特定居住用宅地等) 80%減額 330㎡まで
事業用地(特定事業用宅地等) 80%減額 400㎡まで
貸付事業用地 50%減額 200㎡まで(※条件厳しめ)
■対象になる土地の種類
① 特定居住用宅地等(自宅)
- 被相続人が住んでいた土地
- 配偶者、同居していた子などが引き続き居住する場合に対象
② 特定事業用宅地等(事業)
- 被相続人が事業に使っていた土地
- 相続人が事業を引き継ぐ場合に対象
③ 貸付事業用宅地等(賃貸)
- 被相続人がアパートや駐車場などに貸していた土地
- 相続人が貸付事業を継続する場合(※要件厳しめ)
■具体例
たとえば、自宅の敷地評価額が6,000万円で、面積が330㎡以内の場合:
◆ 評価額 6,000万円 ×(1 - 0.8)= 1,200万円に圧縮!
→ この1,200万円に対して相続税がかかるため、大幅に節税できます。
■適用を受けるための主な要件(例)
自宅用地 相続人が配偶者 or 同居していた子などで、その後も住み続ける
事業用地 相続人が事業を継続する意思と実態がある
貸付用地 相続開始前3年以内に貸付を開始したものは原則対象外 など
※配偶者が取得する場合は、無条件で適用可能(例:自宅)
■手続き・申告について
この特例を使うには、相続税の申告書に特例の適用を申請する必要があります。
忘れると適用できないので要注意です!
■まとめ
メリット 土地の相続税評価額が最大80%減額
対 象 自宅、事業用、貸付用の土地(条件あり)
要 件 居住・事業継続、面積制限など
手続き 相続税申告で適用申請が必要
◆参考資料:国税庁「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」
長期譲渡所得と短期譲渡所得
不動産などの資産を売却する際にとても重要です。「長期譲渡所得」と「短期譲渡所得」は、資産を保有していた期間(所有期間)によって分かれるもので、それによって税率も大きく変わります。
■ 長期譲渡所得 vs 短期譲渡所得
◆短期譲渡所得
5年以下 短期間の所有での売却。投機的とみなされ、税率が高い。
約39.63%(所得税30%+住民税9%+復興特別所得税)
◆長期譲渡所得
5年超 長く保有した資産の売却。優遇税率が適用される。
約20.315%(所得税15%+住民税5%+復興特別所得税)
■ 所有期間のカウント方法
- 譲渡した年の1月1日時点で、所有期間が5年を超えていれば「長期」、5年以下なら「短期」となります。
- カウントは「取得日から譲渡した年の1月1日まで」です。
■ 譲渡所得の計算式
譲渡所得=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除(※条件付き)
その後、長期 or 短期に応じた税率が適用されます。
■ 特別控除の例(長期譲渡所得で適用されやすい)
- 居住用財産の3,000万円特別控除
- 10年超保有の軽減税率の特例
- 買換え特例(一定条件で課税繰り延べ)
■ 補足
- 不動産の「登記日」ではなく実際の引渡日(契約成立日)が取得日とされます。
- 相続や贈与で取得した場合は、元の所有者の取得日・取得価格を引き継ぐルールがあります(取得費引継ぎ制度)。
空家の3,000万円特別控除 耐震リフォーム
■相続人3人以上は2,000万円控除に
2024年(令和6年)1月1日以降に対象となる「相続した空き家」を売却した場合で、相続人が3人以上いると、これまでの「3,000万円の特別控除」が一人あたり2,000万円に引き下げられます。
これは2023年度の税制改正による変更で、控除額の減額とともに一定の要件が緩和されています 。
◆ ポイントまとめ
◆変更前(~2023年12月31日の譲渡) 一人あたりの控除額:3,000万円
譲渡前整備が必須(耐震改修や解体)
◆変更後(2024年1月1日以降の譲渡) 相続人が2人以下 一人あたりの控除額:3,000万円
相続人が3人以上 一人あたり:2,000万円
譲渡から翌年2月15日までに買主が工事すればOKに
◆該当するかを確認する方法
- 譲渡日が2024年1月1日以降であること
- 相続人が3人以上いるかどうか
- 相続後3年以内か、かつ譲渡期限が令和9年(2027年)12月31日までに完了
- 空き家が対象要件(築年数・用途・耐震等)を満たしていること
これらの条件を満たす場合、控除額は通常の3000万円ではなく、2,000万円になりますのでご注意ください。
■国税庁公式解説より(改正内容抜粋)
被相続人居住用家屋等の譲渡所得の3,000万円特別控除の特例については、
譲渡時までに耐震改修工事が完了していない場合でも、譲渡日から翌年2月15日までに買主が耐震改修を完了し、証明書を取得したときは適用可能 となる。(令和6年度税制改正)
✔️ 令和6年4月1日以降の譲渡分で
✔️ 買主が翌年2月15日までに耐震改修+証明書取得する
■特例の適用を受けるための要件ハの(イ)(ロ)(ハ)の(ロ)
(ロ) 譲渡の時からその譲渡の日の属する年の翌年2月15日までの間に、一定の耐震基準を満たすこととなったこと。
■空き家の3,000万円特別控除を使うには、一定の条件のもと、
売却前に耐震リフォームをするか、建物を解体して土地として売却するという要件が含まれています
■ ポイント:売却前の「耐震改修」または「解体」が必須
これは、旧耐震基準の建物(昭和56年5月31日以前の建築)が多く老朽化しており、そのまま流通させると安全面で問題があるためです。
そのため、以下のいずれかをしなければ、3,000万円控除は使えません。
① 建物を残して売る場合
- 現行の耐震基準に適合するようにリフォーム(耐震改修)してから売却する。
② 建物を壊して土地として売る場合:
- 売却前に建物を解体して更地にする。
■ 国税庁の公式記載(要約)
昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、譲渡の時までにその建物を次のいずれかの方法で処理していること
・耐震基準に適合するように補強工事を行うこと
・除却(取り壊し)して土地のみを譲渡すること
■ 補足:耐震リフォームにかかる費用と手間
- 耐震リフォームには100万円〜200万円以上かかることが多く、手続きも煩雑です。
- そのため、実務では建物を解体して更地で売る方が簡単かつ確実というケースが多く見られます
つまり、「解体 or 耐震リフォーム」は3,000万円特別控除を受けるための重要な要件の一つです
売却を検討されている場合は、早めに相談して下さい。