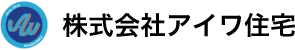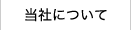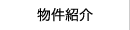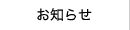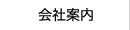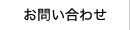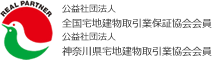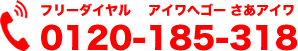さまざまな種類の保険
保険にはさまざまな種類があり、それぞれが特定のリスクに備えるための仕組みです。日本で一般的な保険の種類を簡単に説明します:
✅生命保険(せいめいほけん)
万が一の死亡や高度障害時に保険金が支払われ、遺族の生活を支える保険です。
- 定期保険:保険期間が決まっている(安価)
- 終身保険:一生涯保障される(貯蓄性あり)
- 収入保障保険:毎月一定額が支払われるタイプ
✅医療保険・がん保険
病気やけがによる入院・手術に対する給付金が支払われます。
- 医療保険:一般的な入院や手術に対応
- がん保険:がんと診断されたときの治療費用をカバー
✅ 自動車保険(じどうしゃほけん)
自動車事故に備える保険で、加入が義務づけられている「自賠責保険」と、任意で加入する「任意保険」があります。
- 対人・対物賠償
- 車両保険
- 人身傷害補償など
✅ 火災保険・地震保険
自宅が火事や自然災害で被害を受けた場合に補償されます。
- 火災保険:火災・風災・水漏れなど
- 地震保険:地震・津波による損害(火災保険とセットで契約)
✅ 介護保険(かいごほけん)
公的保険制度の一部で、40歳以上が加入対象。要介護になった際に介護サービスを受けるための支援です。
ご自身のライフステージや目的に応じて、適切な保険を選ぶことが大切です。
新耐震基準
「新耐震基準」とは、日本で1981年(昭和56年)6月に施行された建築基準法改正によって導入された耐震設計の基準です。この基準は、建物が震度6強〜7程度の大地震でも「倒壊・崩壊しない」ことを目指しています
■背景と特徴
- 旧耐震基準(1971年以前)
→ 「震度5程度の地震で損傷しないこと」が目安
→ 大地震時の倒壊リスクが高い - 新耐震基準(1981年以降)
→ 「震度6強〜7でも倒壊しない」ことが基本方針
→ 構造体の設計に鉄筋や壁量の強化が盛り込まれた
■築年数での判断目安
1981年6月以前 旧耐震基準
1981年6月以降 新耐震基準(重要)
2000年以降 より厳格な改訂あり
■注意点
- 新耐震基準以前の建物でも耐震改修工事で補強が可能です。
- マンションや戸建ての購入時は「竣工日」や「検査済証」の確認が大切です
準確定申告
「準確定申告」について、ご説明します。
■準確定申告とは?
「準確定申告(じゅんかくていしんこく)」とは、亡くなった人(被相続人)が生きていた期間の所得について行う確定申告のことです。
通常の確定申告は本人が行いますが、亡くなった場合には、相続人が代わりに行う必要があります。これが「準確定申告」です。
■なぜ必要なの?
亡くなった方が、亡くなる年の1月1日から死亡日までに得た収入(給与所得・年金・事業所得など)があった場合、それに対する所得税や住民税を正しく申告・納税する必要があります。
■誰がやるの?
準確定申告は、相続人全員の連名で行います。
ただし、相続人のうちの1人が代表して提出することも可能です。
■提出期限は?
被相続人が亡くなった日から 4か月以内 に、税務署に提出しなければなりません。
例:4月15日に亡くなった場合 → 8月15日が提出期限
■提出先は?
被相続人の住所地を管轄する税務署です。
■必要な書類:
- 準確定申告書(確定申告書の様式を使用)
- 被相続人の源泉徴収票や医療費控除の明細など
- 相続人の署名または「付表(相続人の一覧)」の提出
■申告が必要なケース例:
- 亡くなった方が給与所得者で、年末調整されていない
- 年金収入が400万円を超えていた
- 医療費控除や雑損控除を受ける予定だった
- 不動産や株の譲渡益があった
■注意点
- 準確定申告によって還付金が出る場合もあります。過払いの税金は、相続人が受け取れます。
- 準確定申告とは別に、相続税の申告・納付(原則として死亡後10か月以内)も必要です。
終身医療保険
終身医療保険は、人生を通じて医療リスクに備えることができる保険で、多くの方に選ばれている保険商品です。以下では、終身医療保険の主な利点をわかりやすくご紹介します。
■ 終身医療保険の利点(メリット)
① 一生涯保障される
- 契約期間に終わりがなく、死亡するまで保障が続く。
- 高齢になってからの入院や手術にも対応できる。
② 保険料が一定(多くは「終身払」または「短期払い」)
- 若いうちに加入すると、その時点の保険料が一生変わらないケースが多い。
- 老後の医療費不安に備えやすい。
③ 解約返戻金があるタイプもある(※商品による)
- 掛け捨て型ではないタイプなら、途中で解約した際に戻るお金(返戻金)があることも。
- 将来的な資金としての活用も可能。
④ 高額療養費制度を補完できる
- 公的医療保険だけではカバーできない差額ベッド代・先進医療費・通院費用などにも備えられる。
⑤ 特約で保障をカスタマイズ可能
- 例:がん特約、先進医療特約、通院保障などをニーズに合わせて追加できる。
- 自分や家族の病歴に応じて柔軟に設計可能。
■ こんな人におすすめ
▲若いうちに加入したい人 保険料が安く、将来の医療リスクに早めに備えられる
▲老後の医療不安がある人 高齢期の入院・手術費用への備えができる
▲長期の安心を求める人 保険の更新手続きが不要で、安心感が持てる
⚠️ 注意点(デメリットもチェック)
- 保険料は定期型より高め(長期保障のため)
- 若いうちに医療費がかからなければ、元が取れないと感じることも
- 加入時の健康状態により、加入できない・制限がある場合も
土砂災害警戒区域と盛土法の調査
- 市役所の調査で足りない、県土木事務所調査
- なぜ県の所轄になるのか
- 土砂災害警戒区域(イエローゾーン)や特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づいて都道府県知事が指定します。
- 盛土規制法(盛土規制区域)も同様に、都道府県が管轄しています。
- そのため、最新かつ正式な区域情報や図面は県土木事務所(または県の都市計画課など)にしかありません。
- 市役所でできること
市役所は直接の所轄ではないため、「公式な証明」や「最新図面の交付」は基本的にできませんが、
次のようなことはできる場合があります。
- 都市計画課や建築指導課で、参考資料として区域図を閲覧できることがある
→ 市が県からデータを受け取っている場合 - ハザードマップ(防災課・危機管理課)での確認
→ 土砂災害・浸水・津波などの危険区域を市民向けに案内 - 担当課から県土木事務所への電話確認の依頼
→ 市役所の窓口職員が、直接県に問い合わせてくれるケースもあります
- 時間の問題への対応策
- 事前に県土木事務所へ電話予約・メール依頼
→ 資料を先にPDFで送ってもらえる場合があります - 市役所調査の前に、午前中に県へ確認
→ 先に県の資料を押さえておけば、市役所での調査と照合可能 - 不動産調査代行業者を活用
→ 平日16時までに行けない場合の代替策として有効
- まとめ
- 市役所では公式な証明は出せないが、参考情報やハザードマップの提示は可能な場合がある。
- 正式な調査結果や証明書が必要なら、必ず県土木事務所で確認する必要がある。
- 時間が合わない場合は、事前予約・資料送付依頼・代理人調査で対応するのが現実的。
法定相続情報証明制度
「法定相続情報証明制度(ほうていそうぞくじょうほうしょうめいせいど)」について、ご説明します。
■法定相続情報証明制度とは?
「法定相続人が誰なのか」を法務局が公的に証明してくれる制度です。
相続の手続き(銀行・証券・不動産登記など)では、通常、戸籍を何通も提出する必要がありますよね?
それを簡略化するために、「法定相続情報一覧図」という1枚の証明書を使えるようにしたのがこの制度です。
■どんなときに使える?
相続が発生したあとの、以下のような手続きで利用されます:
- 銀行口座の解約
- 不動産の相続登記
- 株式・証券の名義変更
- 相続税申告 など
■どんな書類がもらえるの?
法務局が発行する「法定相続情報一覧図の写し(登記官の認証付き)」です。
これを各機関に提出すれば、戸籍一式を毎回出さなくて済むようになります。
■手続きの流れ
- 戸籍一式を取得(被相続人の出生から死亡まで、相続人の現在の戸籍など)
- 「法定相続情報一覧図」を作成
- 登記所(法務局)に申出
- 法務局が確認・認証し、写しを交付
※手続きは無料!
※司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
■メリットまとめ
戸籍提出が1回で済む 毎回戸籍をコピーする手間がなくなる
無料で取得できる 認証手数料も不要
何枚でも写しを交付してもらえる 複数の金融機関に同時提出できる
手続きがスムーズに進む 書類チェックの時間が短縮
■注意点
- 法定相続情報一覧図の内容にミスがあると、再提出が必要
- 法定相続人が確定していないと使えない(相続放棄がまだの場合など)
■どこで手続きできる?
法務局(登記所)で、郵送や窓口で申出可能です。
全国どこの法務局でもOK(一部制限あり)
後見人制度
成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない人を財産の管理や契約の手続きなど、自分で行うことが難しい人が不利益を受けないように、法律的に支援する制度です。家庭裁判所が選任した「成年後見人」などが代わってサポートします。
成年後見制度は、大きく分けて以下の3種類に分かれます
1. 法定後見制度
本人の判断能力の程度に応じて、次の3つに分類されます。
- 後見:判断能力がまったくない人
- 保佐:判断能力が著しく不十分な人
- 補助:判断能力が不十分な人
これらの場合、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任します
2. 任意後見制度
将来、判断能力が低下したときのために、あらかじめ自分が信頼できる人(任意後見人)と契約を結んでおく制度です。本人の判断能力が低下してから、契約が効力を持ちます
3. 後見人の役割
- 財産管理(預貯金、不動産など)
- 契約の代行・同意(施設入所契約など)
- 医療や福祉サービスの手続き など
制度を利用することで、本人の生活と権利が守られ、家族の負担も軽減されます
残置物
残置物
残置物とは、賃貸物件や売買物件などで契約終了後、
前の入居者・所有者が置きっぱなしにした家具・家電・荷物などを指します。
一般的には以下のようなケースで発生します。
- 賃貸の退去時に持ち帰られなかった家具や家電
- 売買で引き渡し後に前所有者の荷物が残っている場合
- 借主が夜逃げ・行方不明になった場合の荷物
法的な扱い
法律的には「所有権は元の持ち主にある」ため、勝手に処分するとトラブルになります。
特に賃貸契約の場合は、
- 借主や相続人に連絡
- 一定期間保管
- 内容証明などで通知 といった手続きを踏む必要があります。
処分の流れ(例:賃貸)
- 持ち主に通知(電話・郵送・内容証明)
- 一定期間の保管(通常は1〜3か月程度)
- 持ち主が引き取りしない場合 → 合意書や裁判所の手続きを経て処分
注意点
- 残置物を勝手に売る・捨てると損害賠償請求される可能性あり
- 生ごみや危険物は衛生上・安全上の観点から早急に行政指導で処理可能な場合もあり
- 空き家や相続案件では「残置物撤去業者」を使うケースも多い
建蔽率容積率
建ぺい率(けんぺいりつ)と容積率(ようせきりつ)は、土地にどれだけ建物を建てられるかを定める重要な指標で、都市計画法および建築基準法によって規定されています
■ 建ぺい率(けんぺいりつ)
■ 定義
「敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た面積)の割合」のこと
■ 計算式
建ぺい率(%)=(建築面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、建築面積が50㎡なら、建ぺい率は50%
■容積率(ようせきりつ)
■定義
「敷地面積に対する延べ床面積(各階の合計床面積)の割合」のこと。
■ 計算式
容積率(%)=(延べ床面積 ÷ 敷地面積)× 100
■ 例
敷地面積が100㎡、延べ床面積が150㎡なら、容積率は150%
■ 規制内容は用途地域ごとに異なる
第一種低層住居専用地域 建ぺい率50% 容積率100%または200%
商業地域 建ぺい率80% 容積率400%または500%
工業地域 建ぺい率60% 容積率200%または300%
※角地や防火地域の条件によって緩和される場合あり。
■土地を買う前、家を建てる前には、必ず都市計画図や役所の確認が必要です。
道路幅員による容積率制限とは
1. 道路幅員による容積率制限とは
建築基準法第52条第2項では、敷地が接している道路の幅が狭いと、建物の容積率(延べ床面積の制限)が自動的に下がるというルールがあります。
これは、日照・採光・通風などを確保するためです。
2. 基本ルール
容積率は、都市計画で定められた指定容積率と、道路幅員による制限値の小さい方が適用されます。
道路幅員による制限値は、以下の式で計算します。
容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数容積率の限度 = 道路幅員(m) × 制限倍数容積率の限度=道路幅員(m)×制限倍数
この制限倍数は、用途地域によって異なります。
3. 制限倍数
- 住居系の用途地域(第一種・第二種低層住居専用、第一種・第二種中高層住居専用、第一種・第二種住居、準住居、田園住居)
→ 倍数は 4/10(=0.4)、つまり「道路幅員 × 0.4 × 100」でパーセント化
例:道路幅6mなら 6 × 0.4 × 100 = 240% - その他の用途地域(近隣商業、商業、準工業、工業、工業専用)
→ 倍数は 6/10(=0.6)
例:道路幅6mなら 6 × 0.6 × 100 = 360%
4. 適用例
- 用途地域:第一種住居地域(倍数0.4)
- 指定容積率:300%
- 道路幅員:5m
計算:5 × 0.4 × 100 = 200%
→ この場合、300%ではなく**200%**が容積率の上限となります。
5. 注意点
- 接道している道路が複数ある場合は、幅員が最も広い道路側で計算します。
- 前面道路が4m未満の場合は、セットバック後の幅員で計算します。
- 指定容積率が道路幅員制限より低ければ、道路幅員制限は関係ありません。